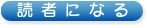久しぶりのデート
梅雨の晴れ間。
とっても気持ちのいいお天気。
父が「くひとりにいこ」と言いました。
区費?
徴収に?
違いました。
「句碑を撮りに行こう」というこで
「じゃあ、私の車出してくるわ」と言いますと
「いや、わしの車で行こ」と父。
今回は父の運転で北に向いて出発しようと車に乗り込もうとしたその時、北の方から一台の車が、なにげなく見ているとその車を運転しているお方は
えべっさん!
たしかに、えべっさん!優しい笑顔で会釈してくださいました。
もうびっくり!
こんなところでお会いするとは、なんかいい事ありそう。
余呉湖に向いて出発。

余呉湖の天女ですね。

「お父さんの見たかった句碑ってこれ?」
「いや、また別や」

これは何と書いてあるのか読めません。

一応、説明の書いてある石も写してきましたが、残念ながら読めず

これは読めます。

こうしてみるとたくさんの句碑が自然石に刻まれています。
余呉湖を周って感じたままを俳句にされたのでしょうね。
「ところでお父さんの見たかったのはこの句碑?」
「いや、どこやったかなぁ~」と父。



川並の野神さんの立派なケヤキ
この木も御神木だそうです。

いやぁ~、いいお天気の余呉湖、天女が舞い降りてきそうな美しさ。
その後、余呉の知り合いの家に聞きに行って、父のお目当ての句碑を求めてドライブを続けます。

この紫陽花園の向こう側らしい。

「あった、あった、この句碑や!」と父。

『鳥共も 寝むっているか 余呉の湖』
寒い寒い冬は鳥たちも寝ているのか静かな余呉の湖という意味かな。

斎部路通(いんべろつう)の句碑

松男芭蕉の門人だそうです。
父はこの句が好きで、「後で写真を焼いてくれ」と頼まれました。
その後余呉湖を後にして塩津方面へ

釣りをされている人発見。

おっ!小鮎がつれた。
うぐいがいっぱい泳いでいます。
雨の後なので少し水は濁っていますが、小鮎もいっぱい泳いでいます。
おもむろに車に戻る父。
な~るほど、父の車で行こうと言った訳がようやくわかりました。

車から釣竿を持ってくる父。

毛針で釣るのだそうです。
あんなにいっぱいいるのに全然釣れない父。

あえなく、撤退。

もう一つの穴場へ。
ここは多いときは魚が飛び上がって跳ねているそうです。
けっこうたくさんの釣り人たち。

ここのところを魚があがるのだそうです。
しばらく釣り人たちの様子を見てから川を後にしました。

塩津の燈台。
江戸時代のものだそうです。
この道路の辺りまで、琵琶湖がきていたのではないか父は言います。

霊験あらたかな塩津神社。
その後西山へ寄りました。
30年もの長い間、うちの店に働きに来てくれていた布施さんというおばさんがおられます。
父より3歳ほど上なので、御歳86歳。
いつも西山から自転車で畑で取れた野菜や、花などを届けてくださっていましたが、さすがに自転車では危ないので、最近はお顔をみておりませんでしたので、私がすごく会いたくて、寄ってもらいました。

とても久しぶりでしたが、とってもお元気そう。
毎日畑へ行って、野菜を作ったりお花を作ったりされているからなのでしょう。
長男はとくによくお守りをしていただきました。

綺麗なお花。

「会いたかったわ~」とおばさん。
「また息子も連れて来ますね」と私。
お野菜やお花をいっぱいいただいて帰ってきました。
いいお天気の久しぶりの父とのドライブでした。
ちょっと、運転 怖かった。へへ
鯉のこまぶし
父から、自分の車にはスタットレスタイヤがはまっていないので、私に余呉の川並まで乗せていってほしいと頼まれました。
久しぶりの父とのドライブです。
昨日、主人の福島に住むお姉さんが法事に帰って来られた時にお土産に持たせてあげようと父が頼んでおいたそうです。
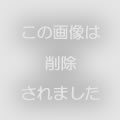
冬の賤ヶ岳もなかなか風情があります。
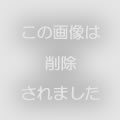
余呉湖も薄く氷の張っているところがありました。
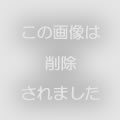
わぁ~、たくさんの人。
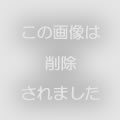
わかさぎ釣りのシーズンですね。
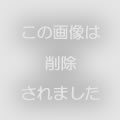
さすが余呉、木之本より雪が多い。
小雪が舞ってるし。
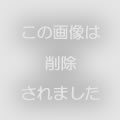
余呉湖畔の民宿『みずうみ』

父はここで頼んでいたようです。
本当は鮒のこまぶしをと頼んだそうですが、鮒が手にはいらなかったそうで鯉のこまぶしになりました。

肉厚でおいしそう。
久しぶりに帰ってくる娘に食べさせてあげたい親心ですね。
私もお相伴にあずかったことは言うまでもありません。へへへ
西野隧道
お天気がよかったので父とドライブです。
高月町の有名な史跡の一つ、西野隧道を見に行くことに。
子供が小学校の時に、この西野隧道について調べて、学校で劇をしたことがあったので、名前だけは知っていましたが、本物を見るのは初めて。

このトンネルは2代目の西野隧道。

歩いて通ることができます。

中はちょっとひんやり。

やっと出口です。240mくらいでしょうか。

ここを通り抜けると初代の西野隧道が見られます。
この出口の右側。

西野隧道は1845年に西野恵荘さんによって掘られたトンネルです。これは今から164年前の出来事です。西野隧道はたびたび余呉川の氾濫によって浸水に苦しめられた高月町西野周辺の集落を守るため、氾濫した水をびわ湖へ逃がすために作られたそうです。初代のトンネルは手作業による掘削作業で岩盤の硬さや落石事故により難工事だったと言われています。

この初代の西野隧道も人一人が通れるようになっていますが、父の持ってきてくれた懐中電灯が消えかけていたので、今回はここまで。
子供の話ではコオモリが飛んでたと言っていました。

ゴツゴツとした岩肌がみえます。
これを一人で掘られたのでしょうか。
気の遠くなる話ですね。
これが現在の隧道(余呉川放水路)

小さな魚がピチピチ跳ねています。
昔、父はよくここで釣りを楽しんだそうです。

琵琶湖へと流れていきます。

この西野恵荘さんの銅像があるお寺。
充満寺。

近くにあるとってもすごい史跡でした。
今度は電池の新しい懐中電灯を持ってぜひ初代西野隧道を通ってみたいものです。
北海道?

ここは古橋を越えて、川合を越えて、大見を越えて下丹生、上丹生の奥の洞寿院。
今回は父しか知らないお得意様を私に教えるためやってきました。
上丹生の辺りに一年に一度だけお酒を頼んでくださるお客様がいらっしゃるのだとか。
そのお家を教えてもらいました。その奥にあるのが洞寿院。

不許葷酒入山門。
葷酒の山門に入るを許さず
葷は味が辛く、臭気の強い植物で、ふつう葱、にら,らっきょう、にんにく、薑の五辛をいうもので、このにんにくは臭いがきつく精がつきすぎるのと、酒は酔って修行者の心を乱すもととなるので、出家者に禁じられていて、これは葷酒の牌などと呼ばれているらしいのです。
私は入れませんね。
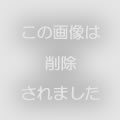
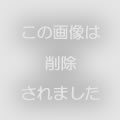
この立派なお寺には今、ご住職がおられないそうです。
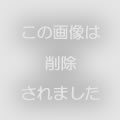
この辺りは昔、いわなとあまごの釣り堀があり釣りも楽しめたようですが、今ではすっかりさびれてため池になっていました。
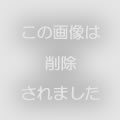
水はとてもきれいなんですけどね。
とち餅製造直売所と看板が上がっていますが、ひっそりしています。
今はもうしていないのかなぁ。
その奥に。

なにやら真っ暗で先の見えないトンネルが。

この湖北に『北海道トンネル』?
通り抜けてみますと、そこには。

綺麗な川が流れています。
ここは父の鮎つりの穴場だったそうで、よくここで夜中まで鮎釣りを楽しんだそうです。
「昔はよく釣れてなぁ」と懐かしそうな父。

湧き水が出ています。

胡桃谷の名水。
ちなみにここに置いてある硝子のコップは、みんなに使ってもらおうと、うちから父が持ってきたコップらしいです。
父らしいですね。

名水を飲む父。しかも手で。(コップは?)
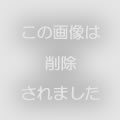
帰りに鮎を何匹も持っているおじさんに会いました。
父が「その鮎どうするんですか?」と聞きますとどうやらこの鮎をおとりにしてうなぎを捕まえるそうです。

川の下へ降りて仕掛けを置きにいくおじさん。
まだまだ自然がいっぱいですね。
何日かしてから父もうなぎが釣りたくなったようで、鮎を仕掛けて一晩たったら骨だけになっていたそうです。素人はなかなかうまくはいきません。残念でした、お父さん。
ころり観音
父が「ちょと車に乗せてくれるか~」
「は~い」
さて今日はどこへドライブ?
ここも木之本の隣の高月町唐川。近くです。
父:「ころり観音さんに行ってみるわ。」
母:「3回参らなあきまへんで~」

本当は、今日7月10日が毎年千日会の日で、今日はお参りの人出がすごいようで、とても近寄れないらしくわざとこの日をずらして参りましたので、ひっそりとしておりました。
千日会の日に参りますと千日参拝したのと同じご利益があるそうです。赤後寺の本尊は、国の重要文化財に指定されている千手観音と聖観音の2体の観音で、「厄を転じて利を施す」ご利益があると言われ、別名「コロリ観音」として信仰を集めています。

あっ!ほんとうだ。転利観音(コロリ)って書いてあります。

立派な鳥居をくぐります。

鳥居をくぐって階段をあがると神社があります。
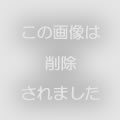
綺麗な色のがく紫陽花。

何回来ても立派やなぁ、と見上げる父。

数珠のでっかいの。上に滑車がついていてくるくる回ります。

父は念入りにお参りをしています。
「自分の命が尽きる時はコロリとまいらせてください。」
そんなぁ~まだまだコロリなんて嫌ですよ!
ここは神仏合体で神社とお寺が並んで建っています。
片方では柏手を打ってお参りしますが、こちらはそのままお参りします。

この神社にも樹齢何百年もたっている立派な杉の木がありました。

本殿の方に倒れないように鉄線で引っ張られています。
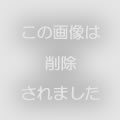
「ところでお父さん、ここへは何回くらいお参りしてるの?」と聞きますと、
「10回位かな」
お母さんが3回参ると願いが通じるって。
「3年続けて参るとコロリといけるらしい。わしはバラバラと10回やからまだまいれんのやな」
人間いつかは誰にでも平等に死は訪れます。その時は誰の世話にもならず、コロリとあの世にいきたいとは誰しも思うこと。
だけど父や母にはずっと長生きしてもらわないと。
私はまだまだ未熟者ですから、教えていただくことがいっぱいありますから。
そんな簡単にコロリといってもらっちゃ困りますよ。