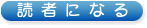輪読?????
今日から、ジーバーぽこぽこさんのグループの一つに入らせていただきました。
今年度はジーバーぽこぽこさんの10周年とかで、11月には記念の会をされるよう。
ジーバーぽこぽこさんは、小学校ごとにグループを作ってらっしゃるのですが・・・・
ある小学校グループさんは、群読をされるそうです。
大型紙芝居をされるグループもあるそうで。
私が寄せていただくグループさんは、朗読劇にしようと。
そして、もうひとつのグループさんは「輪読」をされると。
輪読???
輪読というのは・・・・
数人が一つの本を順番に読んで解釈をし、問題点について論じ合ったりすること
デジタル大辞泉 より
つまり、大学での勉強のように、超難しい本を勉強するときに、その本をいくつかに分割して担当を決め、担当者は、自分の担当するページを読んで要約し、レジュメにして他の人に発表する。
こうして、みんなでその本を分担して要約し、全員で理解するという、勉強の方法なんですよね。
その勉強会のことを「輪読会」とも言うそうです。
ですから
順番に回して読むことを「輪読」とは言いません。
それは、リレーの音読です。
「私たちは輪読をします」
などとおっしゃいますと、まったく意味が違いますから、どうか、順番にリレーで音読していくことを「輪読」と称するのはやめてくださいね~~~~。
ピアノ発表会
ひどっ・・・・
只今、ある作品を練習中です。
数年前に読んだことがある作品ですから、イメージはつかめているはず。
で、録音してみます。
これ大事です。自分の声を録音すること。
最初はびっくりします。「こんな声じゃない~~~」って。
自分の声は、中から聞いている声なので、録音された声と違うんですよね。
でも、慣れます。何度も録音していると、客観的に自分ってこんな声なんだ・・・・
と、慣れるというより、諦めるって感じでしょうか。
で。とにかく、録音して、、、、あまりの下手さに、愕然としております。。。。
あぁぁぁ。練習しなければ。
反省その他いろいろ
毎月のように第一土曜日は、二つのサークルさんの練習日です。
想像して、イメージして~~ と、ずっと言い続けている朗読教室ですから、その甲斐あってか、ただ棒読みされる方は一人もいらっしゃいません。いいですね~~。うれしいですね~~~。
どこをどのように修正しようか?と悩むほどに、良い朗読をされる方も多いので、大変です。
お教室なので、「はい。上手です。」で終わるわけにもいかないので・・・・。無理矢理、重箱の隅をつつくわけです。
読み聞かせも大きく言えば朗読ですから、朗読人口は多い長浜ですが、『朗読文化』 が育っているわけでもなく。
この前の朗読会で、宮沢賢治の「永訣の朝」 の朗読があったのですが、まぁ難しい言葉がたくさんでてくるんですよ。
「あめゆじゅとてちてけんじゃ」なんて、ここいらでは聞きなれない方言ですから、意味が解からないとおもいます。
「おらおらでしとりえぐも」わかりませんよね~。
その他、そうえんいろ あおいじゅんさいのもよう きけん (蒼鉛色 青い蓴菜のもよう 気圏)というような、耳で聞いても意味がよく解からない言葉がたくさん登場します。
そこで「字幕があればよかった」という意見を伺いました。
本当は、「なんか言うてやある言葉はよ~わからんかったけど、なんか感動した」と、言っていただかなければならなかったのです。
これは、読み手のイメージが足りなかったのかもしれません。そこまで指導できなかった私の責任です。
でも!!!!
反面、「永訣の朝」を聴いて、なんかしらんが感動した。そしてその後、「宮沢賢治記念館」に行って妹のことを知って、さらに感動したという意見も伺いました。
このように朗読を聞くということは、文字を確認することではなく、感じていただくことなのですが、、、、
読み手も多くはないですが、朗読の聴き手もまだまだ育ってないのでしょうね。
なので!
もっと朗読を聴いていただく機会をつくらねばっ!! と思うのですよ。
朗読会 というものを、もっとメジャーにしなければっ! と思うのですよ。
場所、場所、場所、場所~~~~~。
どこかいい場所ないですかねぇ?
発表会
かつてうちの息子が習っていたピアノ教室の発表会で、影アナをさせていただいています。
今日、先生から曲目と出演者のお名前とコメントをいただきました。
お名前にはすべてに振り仮名付きでいただきました。
これ、ふり仮名ないと、、、、よめましぇん。
他は 噛んでも(かんだらアカンけど)、名前は間違えられないからねぇ。
そして、悩むのが ソナタOP13 そなたおーぱすじゅうさん? そなたおーぱすさーちーん?そもそも英語????
おぉぉ! Let it Go がある! がっ、これも れっといっとご~ と読むべきか、れりご~と読むべきか?
れりご~~~れりご~~~~ って歌ってしまいそう。
っていうか、おかげでそれ以来頭の中、れりご~~ もしくは ありのぉ~~ままのぉ~~~ が、ぐりぐり廻ってますが。
ということで、影アナ担当は密かに悩んでるんですよぉ。
注文の多い料理店 その2
昨日の続きで、注文の多い料理店についてです。
注文の多い料理店 山猫軒では 張り紙が次々と登場します。
最初は
「どなたもどうかおはいりください。決してご遠慮はありません」
「ことに肥ったお方や若いお方は、大歓迎いたします」
なんていう張り紙で、気をよくした二人の紳士がどんどん中にはいっていくわけですが・・・
髪をととのえろ 靴の泥をおとせ 鉄砲と玉を置け 帽子と外套をぬげ ネクタイピンやめがねなど金属のものをすべて置け・・・・
そして、 ツボの中のクリームを身体にぬれと
そのクリームってのが、『牛乳のクリーム』と書かれています。
次に香水を振りかけろと書いてあるのだけれど、それがどうも『酢』
そして、『塩』をよく揉みこむように書かれています。
それを よく塩でもんだ菜っ葉とまぜて、サラダで食べると・・・・。
ってことは、牛乳のクリームと酢と塩のドレッシングってことでしょうか?
クリーミードレッシングをまぶしたサラダですよね?
宮沢賢治って、なかなかオサレな料理を知ってたんですねぇ。
パリパリの生野菜じゃなくて、よく塩でもんだ菜っ葉をサラダにするところが、やはり時代なのでしょうか。
そういえば。
明治生まれの祖父が、100歳のころ
「あ~~。ありゃぁうまかった。ほうれん草。あれを始めて植えたときに、なんとうまい菜っ葉やとおもたなぁ。
あ、ありゃぁ くえんかった。あれじゃ。あれ。
なんやったかいな。
あーーーーーーー
うーーーーーーー
あーーーーーーー
(5分経過)
トマトじゃ!
ありゃ、くえたもんでなかった。青臭そおて。」
と言うてました。
宮沢賢治のサラダ。どんなのだったのかしら。
注文の多い料理店
 宮沢賢治ですね。
宮沢賢治ですね。
朗読の定番ですね。
ところが、難しすぎて、苦手です。。。。。 クラムボンは笑ったよ とか言われた日にゃ、なんだよっ!クラムボンってよぉぉぉ~~~~。感じですわ。
比較的、解かりやすくって、おもしろいと思うのに「注文の多い料理店」があります。
簡単に言うと、二人の紳士が山で道に迷って辿り着いたレストランで、服を脱げだの、クリームをぬれだのと次々と注文をされ、ついに塩をぬれと言われ、自分たちが料理される食材だと気付くというお話です。
深く読み取ろうとすると、中身の無いお金持ちへの揶揄等等が書かれているであろう作品なのですが、ま、簡単におもしろいお話です。
さて。
この「注文の多い料理店」の後半。
山猫の子分?が、塩を塗らない二人の紳士に向かってこういいます。
『それともサラドはお嫌いですか。そんならこれから火を起してフライにしてあげましょうか』
サラドっていうのは、サラダです。
宮沢賢治の時代は、サラドと、英語っぽく言ってたわけですね。
私はこの文章は
「それとも、サラダは嫌いか?ほんなら、これから火を起して、フライにしたろか?生で食われるよりも、火をとおして喰われた方がええか?」
と解釈しておりました。「フライにしたろか?」と。
ところが、ある方の朗読を聴いていたら
「それとも サラドはお嫌いですか。そんなら火を起して フライにして あげましょうか」
と読まれました。
「フライにして 揚げましょうか?」 って意味に聞こえました。
ここいら弁で言うなら、「パン粉つけて あげたろか?」って感じでしょうか。
それも、アリなのか・・・。と思った。
さらっと黙読してたら、そんなことにこだわりませんよね。
だって、「フライにしたろか?」でも「パン粉つけて 揚げたろか?」でも、どちらも、揚げ物になってお皿に乗るのに替わりないのですから。
でも、朗読すると、読み手の解釈で微妙にニュアンスが変わりますね。
おもしろいでしょ。朗読。
で。
本当はどっちなんでしょうね?
「フライにしてあげましょうか」
朗読講座
今回は、一受講生。
改めて、朗読を教えてもらうと、それはそれは難しいわけで。
次回の朗読サークルさんでは、その様子をおはなししますね。
 やればやるほど、難しい朗読です。
やればやるほど、難しい朗読です。
さて。
今回の講座の会場は、息子のアパートのすぐ近くでした。
講座は朝の9時30分から夕方4時40分まで、お昼休みは1時間。
だったので、お昼ご飯と夕食を息子お勧めのお店につれていってもらって・・・・
といっても、ラーメン屋さんと定食屋さん。

そして、息子の大学を見学。
最近、新しい校舎が増築されたとかで、そこのトイレがごっつい豪華だというので、、、、
 トイレをお借りして。
トイレをお借りして。
っていうか、これって、うちらが払った学費や施設費でできてるのよね。。。。
ということで。
今日は、朗読講座をびっちり受講してきました。
勉強になりましたっ!!!!